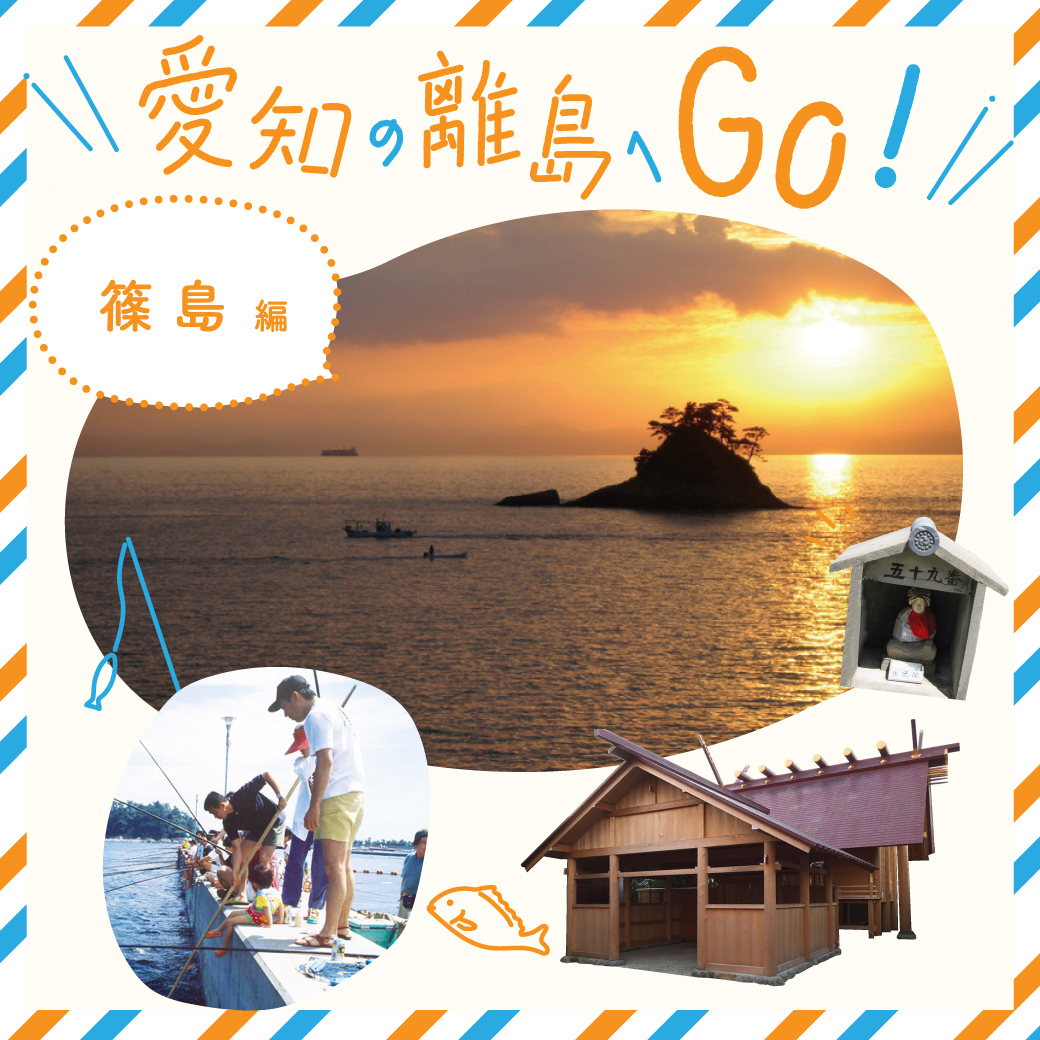おんな城主・井伊直虎ゆかりの地特集
女性でありながら城主をつとめた戦国時代の姫、井伊直虎の物語

2017年のNHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」は、女性でありながら城主をつとめた戦国時代の姫、井伊直虎の物語。数奇な運命に翻弄されながらも、一途な愛を貫き、乱世に立ち向かった女性のいきざまを柴咲コウさんが演じています。そしてわが愛知県も、井伊家ゆかりの地。直虎ゆかりの地を巡って、ドラマの世界をより深く身近に感じてみませんか?
<「井伊直虎」について>
遠江(静岡県)の井伊家に当主・直盛の娘として誕生した一人娘。直盛には、男子の跡継ぎがいないため、分家の亀之丞と娘を婚約させ、亀之丞に井伊家を継がせることにしたが、今川に謀反の疑いをかけられた亀之丞の父が突然殺され、亀之丞も消息不明となった。悲しんだ娘は誰とも結婚できないようにするため、次郎法師と名乗り出家。ところが10年後、亀之丞が帰還…亀之丞は井伊家の跡を継ぐため直親と名を変え、他の女性と結婚してしまう。更にその後、直盛、直親、ほかの重臣たちが相次いで死に、井伊家の男は2歳になる直親の息子・虎松のみになってしまった。誰が井伊家を継ぐか混乱の中、次郎法師が継ぐことに。こうして「井伊直虎」として生まれ変わった、おんな城主の人生が始まった…。
亡き許嫁の忘れ形見である虎松(のちの井伊直政)が、追手から身を隠すために逃れた「鳳来寺」や、井伊家を支えた“井伊谷三人衆”のひとり・鈴木氏の居城「柿本城址」、桶狭間の戦いで今川軍の先鋒の大将を務めた直虎の父・直盛が命を落とした「桶狭間古戦場」など、愛知県にも直虎を取り巻く人々のドラマがあります。戦国の世を駆け抜けた直虎たちに思いを馳せて、愛知の旅を楽しんで。
鳳来寺【新城市】
亡き許嫁の忘れ形見である虎松が、追手から身を隠すために逃れたのが愛知県新城市にある鳳来寺。のちに家康公を支える重臣として、徳川四天王と呼ばれるようになった直政(虎松)の幼少期は、この地で育まれました。
近くのおすすめスポット
- 【新城市】新城設楽原歴史資料館
--戦国と幕末、日本の行方を決定づけたポイントを紹介-- -
新城と言えば、火縄銃を用いた戦法で戦国時代の分岐点となった「長篠・設楽原の戦い」。資料館では、戦国の行方を決める、文字どおりの決戦となったこの合戦の経緯、火縄銃の果たした役割などを展示しています。
- >> おすすめスポット詳細を見る
柿本城跡【新城市】
標高190mの子路山(しろやま)山頂付近にある城跡。井伊家を支えた井伊谷三人衆のひとり、鈴木重勝が築城したと言われています。城の大きさは150四方で、主郭があり、その一段低い場所に腰曲輪が配置されています。土塁などはなく、防御性の低い城と考えられています。ここへは、「道の駅 三河三石」の裏手にある満光寺の脇から徒歩10~15分ほどで登城できます。
近くのおすすめスポット
- 【新城市】満光寺庭園
--景観を 1年中楽しむ事ができる-- - 本堂に十一面観世音菩薩が祀られている、奥三河七観音霊場の五番寺です。元々は天台宗のお寺として建立されたものの、一度戦火に焼かれ、その後曹洞宗のお寺として再興したそうです。このお寺には徳川家康にまつわる有名な逸話も残されています。
- >> おすすめスポット詳細を見る
宇利城跡【新城市】
標高165m、山頂近くにある中世中ごろの山城で、今川氏に属した城主の熊谷実長が、三河統一を目指す松平清康(家康の祖父)の攻撃を受けました(宇利(城)の戦い)。その戦いで、熊谷氏は冨賀寺の裏山に陣を構えた清康に、宇利城の大手門(正門)や搦手門(城の裏門)から攻め入られ、落城しました。1569年、武田氏の攻撃に耐えて家康より戦功を讃えられた近藤康用(井伊谷三人衆のひとり)は、1581年の家康による遠江平定のあとに柿本城へ居城を移しています。
近くのおすすめスポット
- 【新城市】長篠城址史跡保存館
- 長篠城址史跡保存館は、「長篠の戦い」に関する資料を保存・展示し、この地の歴史を伝えています。「長篠城」の城址は国指定史跡や「日本100名城」に選ばれており、また保存館周辺にも合戦にまつわる数々の史跡が残されているという大変興味深い土地です。
- >> おすすめスポット詳細を見る
桶狭間古戦場公園(父直盛の死)【名古屋市】
井伊直虎の父、直盛が出陣した「桶狭間の戦い」。
合戦では今川軍先鋒隊として約1000人程の井伊直盛隊が出陣しましたが、この戦いで井伊直盛は戦死、重臣16名を始め、井伊軍も全滅しました。
公園内には桶狭間合戦当時の地形を模した立体地図が作られており、その中に「井伊直盛の陣」を見ることができます。
公園から西へ300mほどに「桶狭間巻山」という地名が残っていますが、井伊直盛の陣地が、織田軍に包囲された(巻かれた)ことから「巻山」と名付けられたと云われています。
近くのおすすめスポット
- 【名古屋市】有松・鳴海の古い町並み
--風情漂う東海道を歩いてみよう-- -
有松のまちは、慶長13年(1608)に尾張藩の奨励によってつくられました。耕地も少なかったため、副業として絞染めを工夫したのが有松絞のはじまりです。ところが天明4年(1784)、大火により村の大半が焼失するという災難に見舞われました。復興をはかるなか、建物は火災に備えて漆喰を厚く塗り込めた塗籠造とし、萱葺き屋根に変わって瓦葺が使用されました。今も当時の面影を残した町家が並び、有松地区ならではの風情を漂わせています。
- >> おすすめスポット詳細を見る
桶狭間古戦場伝説地・高徳院【豊明市】
450余年前、日本の歴史が大きく動いた場所を一目見よう
高徳院のある場所は、戦国時代には寺はなく高台となっていて、桶狭間の戦いには、今川義元の本陣が置かれた場所といわれています。毎年6月に行われる桶狭間古戦場祭りは、この高徳院の駐車場で行われ、ここで散った多くの武将たちの魂を慰霊します。
近くのおすすめスポット
- 【名古屋市】有松・鳴海絞会館
-
日本の郷土文化、有松絞りの歴史や、絞りの実演が見どころです。
有松絞りの作品を購入したり実際に絞りの体験をすることもできます。 - >> おすすめスポット詳細を見る